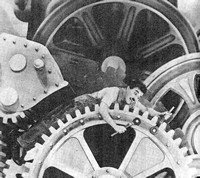話題:連載創作小説
―Unplugged short story-2A ―
1969年 パリ 初夏。
セーヌ左岸から少し離れた、落ち着いた雰囲気の裏通りに一軒の楽器店、兼、工房があった。店を入ってすぐの狭い販売スペースには数台のピアノがところ狭しと置かれ、壁にはヴァイオリンやヴィオラなどの弦楽器が掛けられている。奥には簡素なレジ場があり、その背後には分厚い一枚の壁を挟んで製作や修理の為の工房があった。
店の主はセーヌ左岸には珍しい日本人の男性だった。年の頃は五十前後だろうか。小柄な痩せた男であったが、引き締まった肌や鋭い眼光はどこか強靭な精神性を感じさせていた。
普段、店に客の姿がある事はあまりない。通りがかりの人間が物見がてらにふらりと店の扉をくぐる事はあるが、楽器に貼られている値札を見た途端、あたかも急な用事を思い出したかの如く一目散に店を飛び出すのだった。
しかし、もしも彼らが店内に置かれたヴァイオリンやピアノを試しに弾かせて貰ったならば、その優雅で深い音色に腰を抜かした事だろう。男の作る楽器には、その高い値段に見合うだけの価値が間違いなくあった。そして、その価値を知る人たちがこの店の財政を支えていた。その中には著名な音楽家や文化人、芸術に造詣の深い財界の人間や王公貴族などが含まれていた。
そんな、初夏のある日。
男の工房を一人の老貴婦人が訪ねて来た。やや時代がかった上品な白いサマードレスに同じくツバの広い白の帽子、手には淡い花柄の日傘がたたまれている。
彼女がやんごとなき身分の女性だと云うのは、壁のヴァイオリンがパイプオルガンでは無いのと同じくらい明白な事柄だった。
老婦人は店頭に置かれている売り物の楽器には目もくれず、開口一番にこう言った。
「実は、見て頂きたい物があります」
「…それは構いませんが」
店主が怪訝な面持ちで答える。女性が身に携えているのは日傘のみである。まさか、その日傘を見て欲しいなどと言い出すつもりではあるまい…。
すると彼女はそんな店主の意を察してか、直ぐに次のような台詞を付け加えたのだった。
「助かりました。では今から楽器を此方へ運ばせます」
見て欲しい物が日傘ではなく楽器である事に安堵しながら店主が訊ねる。
「その楽器は今どこに?」
「表に停めてある車の中です」
彼女が向けた視線の先を見ると、店の前の路上に停車するトラックの姿があった。マットな銀色のシトロエンHトラックだ。
間もなく、上等な黒の背広服に身を包んだ体格の良い四人の男たちがトラックから姿を現したかと思うと、大きな黒い布で覆われた物を荷台から降ろし、既に開けてあった入口の両扉から店内へと運び込んで来た。
「ありがとう」先ず女性は男たちに礼を述べ、次いで「では、布を取り払うように」と申し付けた。
彼女の言葉に従って黒い布が取り払われると、その下から姿を現したのは見るからに古そうな一台のピアノであった。
そのピアノを一目見るなり、店主の身体に雷光のような衝撃が走った。
それはピアノと云うよりは“元ピアノ”、或いは“ピアノのなれの果て”とも云うべき物であった。破損状況がかなり酷い。
しかし、それでも…。店主の目が細く、そして鋭くなる。
「これは…ただのピアノでは有りませんね?」
店主の問い掛けに老婦人が落ち着いた口調で答える。
「ええ。これは、とても古い時代に作られた当時の最高級モデルです」
ところが店主は、その返答に対して首を横に振り、再度質問を投げかけた。
「いえ、私が言っているのは“そういう意味”では有りません。このピアノには独特の空気と時間が染み込んでいる。それは薫りで直ぐに判ります」
「…薫りで?」老婦人の眉が少し持ち上がる。
「そうです。言葉で説明するのは無理ですが、兎に角そうなのです。このピアノには“只ならぬ気配”のようなものが漂っています。或いは“強い想い”と言い換えても良いかも知れない。私が先程『ただのピアノではない』と言った事の本当の意味は、このピアノが過ごして来たであろう“時の深さと濃密さ”を指しているのです」
すると、老婦人の表情は陽光が差したように明るく、希望に満ちたものに変わった。
「やはり…」
彼女はそこで一拍おいてから言葉を続けた。
「…やはり、この店を選んだのは正解だったようです。このピアノを甦らせる事の出来る人間は恐らく世界に何人もいないでしょう。そして貴方はその数少ない人間の一人です」
しかし店主は、そんな賞賛の言葉など耳に届かなかったかのように話の先を続けた。
「それよりも、このピアノがどのような由緒を持っているのか、それをお話し頂きたい。このような特別な楽器を甦らせる為には、楽器そのものについて出来るだけ詳しく知る必要があります。見てくれを復元するだけでは意味がないのです。そういう訳ですので、もし、それをお話し頂けないのであれば、残念ですが修理は御断りさせて頂きます」
きっぱりと云い放った店主だが、内心は内心でまた少し違っていた。職人としての彼の目は半ばガラクタのような状態のオールドピアノを見つめながら、早くも『どの部分からどのように手を付けていくべきか』をレントゲンのように探り始めていたのだった。
《続きは追記からどうぞ♪》