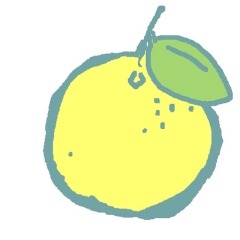[Spring report]
■ヴァスパミナーニエ
人の記憶はCDのようだって誰かがいっていた。
カセットテープのように巻き戻しと早送りで再生するのではない。
CDのように選択し再生する、思い出す。思い出したいことも、勿論思い出したくないことも、記憶のトラックを開けば出てくるのだ。
どんな人であれ、振り返れば過去というひとくくりの同一線上の上に綺麗に並び、ある程度振り分けたCDの見出しから、ああ、あの時の出来事はと選び出す。
「それってちょっと寂しいかも」
俺はカセットテープの方が好き。生きてきた長さがわかるから。ああでも、昨日のことの次に10年前の事を思い出すこともできるのはいいよね。楽しいことの次にまた楽しいことを思い出せたら、幸せなんだよ。
「10年前、あなたはまだ小学生ですね。どんな小学生でしたか?」
「そうだな。急に歌いだすから、変な奴って思われてた、かな」
「正直、私も最初は、関わりたくないタイプの人間だと思ていましたよ」
「あー、うん、それは伝わってた」
「では私が初めてあなたの誕生日を祝ったときのことは?」
「あの時?あ、覚えててくれたんだって。こいつそういうこと興味なさそうだなーって思ってたから。だから、お前の誕生日しつこく聞き出したよね」
「あまり、声高に言える日でもないので」
「でも俺の大切な花が咲く季節だったから、うれしかった」
肉体があるから存在するのではない。その人がそこにあると誰かが認識してくれなければ、存在しないのだ。人が一人で存在できないのは、そういうことでもあると、小さな星の王子さまの物語も、作者が語らなければこの世に存在しないままだった。
悲嘆と孤独の海沿いを歩き続けながら、それでも生きることをあきらめなかったからこそ、誰かが知り、誰かが語る一十木音也は今日まで20年、生き続けている。生き抜いて季節外れの花を咲かせて。
「いまあなたのお母さんのこと、思い浮かべることはできますか」
「できるけど。こんな時に来てもらうのは、ちょっと恥ずかしいな」
かあさんなら、笑って喜んでくれそうだけど。
リズムの違う心臓の音ふたつ。シーツと腕で閉じ込めた躰を、ひとつひとつ味わうように確かめていく。彼の零す、一握りの生命の呻きを知る者は、今、この世界で、私しかいない。
「ねぇ、トキヤは、俺が初めて好きだよって言った時、どう思ったの?」
「あなたが初めて……ああ。私の文字を見て、『真っ直ならんでるけど、気持ちの込め方は熱くて、すごく好きだよ』と言ったときですか?」
「ちぇ、ひっかからなかった」
「初めてはそこでしょう。あなたの好きはそれこそ同じではないと言っていたではないですか。だから私の中にはきちんと分けてありますよ。好きだと言ってくれた時のこと。まあ、もちろん沢山ありすぎて全部は無理ですが」
「全部って言われたら、さすがに怖いかも」
「……そうですね。会って間もないのに、何を言っているのか、心底困りました。どう受け取ればいいのかと」
「うん、あの時の困ったトキヤの顔、すっげーかわいかったから、よく覚えてる」
なにを、と息を奪い、熱をぶつけると、色気のないうめき声が上がった。それにすら興奮する自分もだいぶこの男の色に染まっているのだろう。口の中に閉じ込められた息が逃げようとする、くすぐったい振動が、たまらなく二人の身体が一つになっていることを思い知らせてくれる。
・