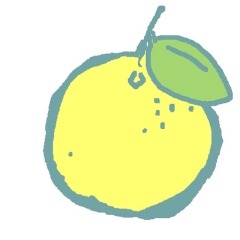頭の中を流れる映画の主題歌が、画面から聞こえる、地を這うようなうめき声に書き換えられる。
眼の前では進まない時間が流れる。
実のところ、そのゲームは実際にプレイしたことがある。
HAYATOの方での、特別親しくもなかった共演者に、
進められて借りた。いや、押し付けられたというべきか。
『そういうのは苦手だと断ればよかっただろう』
『あのままだと、好きなものを言うまで次から次に持ってこられそうだったので。面倒ですから』
『で、ゲームの経験はあるのか?』
『いえ』
マネージャーの苦笑い。
お前も年頃だからな。色々やってみると良いかもしれない。
たまにいる。押し付けと好意を履き違える人間が。
さっさとクリアして返すために、攻略の方法を調べた。
『一日もあれば終わらせてみせます』
進み方は知っている。
だからこそ、アレコレと手探りに進む音也に、口出しをしそうになるのだが。
進めないなら、別の方法を考えなければいけない。
その場にあるものを、全て疑う。
それでも。
眼の前にある物語を、楽しみながら向き合う姿に、己の中の足りないものを知る。
翔にやってもらおうかな。
そう独り言を言っているのが聞こえた。
同じクラスの来栖翔の名前が上がる。
別のクラスとはいえ、音也と翔はいつの間にか親しい仲になっていた。
音也はそうだ。同じクラスの友人にこうやってゲームを借りたり。
いつも誰かと話している。
人懐っこい性格というのだろう。誰にも隔てなく接するから、どうにも人間に好かれやすいみたいだ。
彼の何がそうさせるのだろう。
HAYATOという偶像が目指そうとした形がそこにある。
現に、問い掛けてしまった。
何故彼に相談など持ちかけてしまったのか。
眼の前に広がるゲームが、知っている内容であったばかりに、口実が生まれてしまったからだ。
そうか。
蘇るというだけで、これほど価値観が違うとは驚かされてばかりだ。
「トキヤはどうなの?」
嬉しい?それとも哀しい?
夏の朝に聞く、サイレンの日を思い出す。
人は、生まれた瞬間に死に向かうというが。
その瞬間を明確には選べはしない。
それなら、生まれた意味はなんだろう。
死だけは、約束されたものなのに。
その間に、人は愛を知り、夢を持ち、苦しさと歩む。
だからこそ。
「手段があるならば、それを選ぶでしょうね」
答えをはぐらかしたことは、否めない。
また巡り合う機会があるのなら、あってみたいと思う。
それはどこか、形式上の答えに思えて仕方がない。
可能性があるならもちろん、それを掴もうと思うはずだと自分に言い聞かせているようだ。
「再び会えるのなら。私は手段を選ばないでしょう」
「こんなになっても、会いたいの?」
「……」
悔しくも少し想像してしまった。
眼の前に映し出されている、身体が腐敗し、ドロドロに溶けている。
指先を握れば、きっとズルリと剥がれ落ちるだろう。ぬめる感触を想像して、不快感に眉を寄せた。
手段を選ばないが、それだと、この形状であったとしても受け入れなければいけない。
ほんの一瞬、目の前の男の、グロテスクな姿が浮かんだ。
どうして?と考えるまもなく、消え去る景色に、違和感を感じるにはまだ、この時は足りなくて。
返答に詰まる質問をされたが、それに答えを渡すより先に、音也は、
「その気持を、どう表現するかってことだよね。うーん……うまくいえないけど」
カフェオレで口を濡らしている。
お互い、目の前の、止まった世界に目をやる。
瞳の中を覗くのが怖い。覗き込まれるのを避ける。
「蘇るのは嫌だな」
だってこれだよ。
「好きな子がいたら、わかったかもね」
机の上に置かれた小説を取り、裏表紙のあらすじを眺めている。
「トキヤにはいないの?気になる子」
「別にそれがいい人とは限りません」
そこまでして会いたいと思う相手が、もちろん恋人とは限らない。
なくなった同僚。
死別した両親。
親友。
会いたいと願う人が、どんな人なのか、それは分からない。
読み漁った物語の中でしか、それを体験したことはない。
それに。自分にとって会いたい人は、今はまだ、11桁の番号を打ち込めば、繋がる。
「そっか」
恋人とは限らない。
何よりももどかしいのは、そうか、思い描け無いのだ。
そうしてまで会いたいと思う姿が。
そうだよね、と、凪いだ音が、時折リフレインする。
彼がこの時誰を思い浮かべたのか、それを知るまで。
.
トキヤの読んでいる小説は『黄泉がえり』です。
映画にもなったので、ご覧になった方はいらっしゃると。昔見たことがあったので、それを思い出しましたが、明確な内容は忘れました。
2022-7-16 22:29